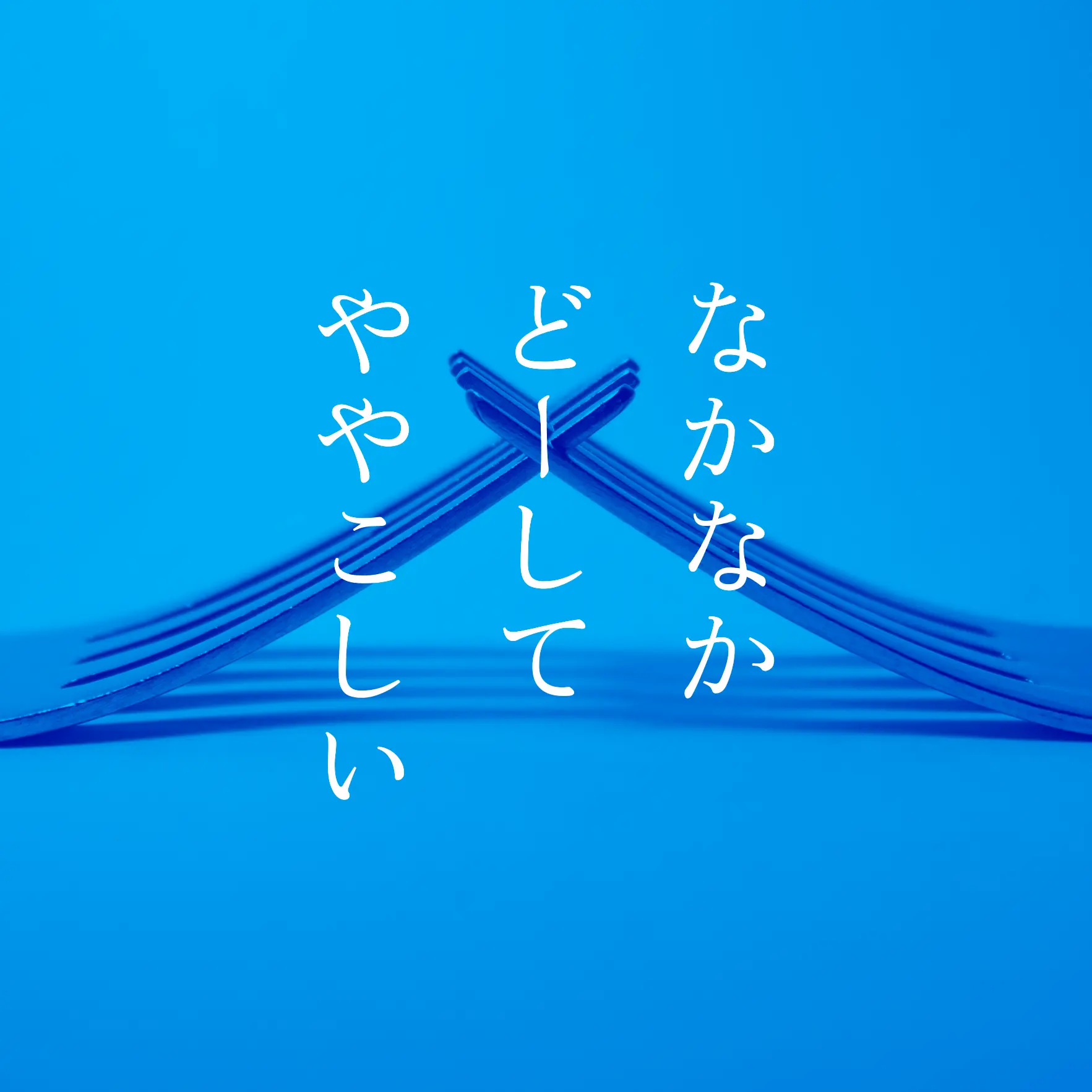屋上病院——医神と雇われバトルナース——
バトルナースヒロインへの屋上オペは第五話だった。『屋上病院』第一巻の第五章。
理不尽に病院を追放された主人公は、廃校屋上での野良手術をきっかけに、屋上での開業を決意する(第一話)。雇った傭兵看護師と意見を対立させたり(第二話)互いに理解を深めたり(第三話)手術で初めて息を合わせたり(第四話)。しかし喜びもつかの間、ヒロインが心筋梗塞を発症しまって——。第五話はヒロインの手術に費やされた。主人公の尽力の甲斐もあってヒロインは一命を取り留め、エピローグで正式に看護師として雇われる。
というライトノベルを執筆した東形京人。心筋梗塞により屋上で死亡。享年、三十四歳。
自殺ではなかった。だがヒロインを屋上に落とそうとした今川大葉は、屋上に落ちて死亡。ヒロインを屋上から落とそうとした衛門虎は、屋上から落ちて死亡。ヒロインを屋上で心筋梗塞発症に至らしめた東形京人は、屋上での心筋梗塞発症によって死亡。
いずれもヒロインは死ななかった。今川大葉のヒロインは、実は堕天使だった。衛門虎のヒロインは、主人公によって自殺を阻まれた。東形京人のヒロインは、主人公の施術で救われた。が、作者は死んだ。自殺ではない。病死でもない。殺されて死んだのだ。
「屋上ものの作者だった」
「たしかに異世界転生ものではなさそうです」
「異世界転生にも屋上はある」
「『けのとと』にもありますね」
ある、などというものではない。鯛焼堂杏子の『時計仕掛けの林檎と蜂蜜と妹。』は今やその代名詞なのである。『けのとと』のヒロインたちは必ず学校屋上で正体を明かす。
黛は白目を剝いて(比喩の一種)鯛焼堂杏子の安否を確認した。速やかに無理を押し通した。鯛焼堂杏子は無事だった。その過程で旅行の計画を知った。黛は何も見なかったことにしようとして、もちろんそのようなことができるわけはなくて、やはり白目を剝く(比喩)羽目になった。
連続ライトノベル作家殺人事件! 次回、温泉旅館の殺人! 作家友達と某市の温泉地に遊びに来た鯛焼堂杏子の運命とは——?
四月二十七日から一週間と少し前、黛は二十一歳に頭を下げた。
「みかど旅館にどうにか転がり込んでくれ」
二十一歳は心底嫌そうに眉根を寄せた。
「二名様でご予約の高橋さま」
「はい、高橋弥勒です」
花宮は常に黛の先を歩き、客室に踏み入り、入るなり畳に座り込んで本を開いた。室内の見分は黛に丸投げした。しかし黛も文句をつけずに部屋の確認と整理を済ませ、五分たって初めて声をかけた。
「高橋、おい」
ちょうど花宮も本を閉じた。
「どうかされましたか日暮先輩」
リュックサックに手を差し入れて、文庫本をしまい、文庫本を取り出す。歯車をあしらったタイトルロゴ。『時計仕掛けの林檎と蜂蜜と妹。』最新二十巻。黛の布教用にして、花宮の新たな愛読書——。
「——なわけねえだろ、あんたのせいで読まされてんです」
「狩りに必要だからって読んだおまえの判断だ」
犯人はともあれ三月から一か月足らずでライトノベル作家三名が殺されている。手段はどうあれ、それぞれのヒロインの身に起きた——起きようとした——事象をまるで再現するかのように。ライトノベル愛好家の黛はこの三という数字を看過できないと判断し、また花宮も判断を下したのである。
「事実ならこれは見立て殺人だ。死因がそれぞれの作品に記されているんです。そのうえ次に死ぬかもしれないやつがわかっていて、どうしたら読まない選択ができるんです?」
「おもしろいだろ」
「娯楽として一定以上の評価を得ていることは疑いません」
愛読者の前で花宮は言葉を選んだが、当人はじとりとした視線を向けた。
「続きが聞きたいなら言いますが」
黛は首を振って、視線をずらした。ただ、表紙が目に入ったから、尋ねてみる。
「イラストか?」
イラスト表紙の美少女ヒロイン。ライトノベルが敬遠されがちな理由の一つだ。愛好家であっても、表紙を隠すために不透明のカバーをつけたり、そもそも外では読まなかったり。黛はどこでも透明のビニールのカバーで読むが、多数派ではない自覚もある。しかし花宮は怪訝な顔をした。
「それ内容と関係あります?」
「——無関係でもない」
コミカライズやアニメ化に際しては、原作の表紙や挿絵を元にキャラクターがデザインされるものだ。あくまで本体は文章だろうが、イラストにも重要な働きがある。
と、そこまで考えて黛も怪訝な顔になった。
「まさか、おまえ——怪物警察だって言うんじゃないだろうな」
「——SNSなんかで稀によく見る『弓道警察』の亜種の意味ならイエス。逆にあなたが楽しめているという事実が理解しかねる部分ですよ」
「——稀によく」
「そこかよ」
「——つまりヒロインの描写が正しくないから楽しめないと」
「弓道経験者にとって正しくない弓道描写がノイズたりえるように、正しくない怪物描写は俺にとってはノイズたりえる。まさか指摘して回るような内容でもありませんが」
そのノイズを、あるとき指摘して回った連中が弓道警察である。たまたま弓道警察が目立っただけで、格闘、狙撃、違法建築、車の寸法、街の構造、野菜の断面、まあいろいろ。たまたま花宮は怪物関係者であったので、
「五巻で登場した専門家が主人公の問題を解決しないことが、今の一番のノイズです」
それはもう十五巻も続いている状態で、今後も解決に向かうことはないだろう。もう一度、題名を声に出して読んでみてほしい。時計仕掛けの林檎と蜂蜜と妹。メインヒロインの人数と性質である。
「べつにクレームなんかはつけません。俺は『ハリー・ポッター』も黙って全巻読みました」
「なんだって?」
花宮は答えなかった。新たに手に取った『けのとと』を開くこともしなかった。あらすじだけ確認すると、またしまって、荷物を持って立ち上がる。
「整理は済んだみたいですね」
温泉宿まで来てまずライトノベルを読み終えた花宮は、他のことを丸投げした黛の礼の一つも告げず、まっすぐ歩いて廊下に出た。「おい」と言われて初めて「ああ、ありがとうございました」と思い出した。そうすると二人は無言になって辺りを見回す。玄関口まで誰ともすれ違わなかった。
初めて見かけた他の客は、受付を済ませた若い男だった。若いといっても黛よりは大分上の、三十路に立つか立ったところか。仕事に疲れた社会人が一人旅に出てきたといった風情だ。あるいは出張かもしれないが、服と荷物がそぐわない。まるきり遊びに来た人間のようだ。体つきも悪くない。何かあれば黛も立ち回りを考えねばならない。べつに術師にも見えないが。滞在期間は重なっている。
「なあ高橋」
黛は僅かに首を動かした。花宮がややあって返事をした。
「どうかされましたか日暮先輩」
「あの人おまえの知り合いか?」
どうしてなどとは尋ねなかった。花宮は押し黙って前を見ていた。受付を終えたばかりの年上の男が、二人のいる方向を見て、手を振っている。
「ま、こ、と、く、ん」
彼は口の動きで花宮を呼んだ。ちょっと笑って、ちょっと走った。ついに二人の前で立ち止まると、ちょっと声をひそめ、うかがうように花宮を見る。
「仕事中だった、かな?」
「ええ。大学の先輩と旅行に来たんです。日暮先輩、この人は——」
「——高木です。よろしくね、日暮くん」
「——日暮です。高木さん」
「その調子で僕のことも、ぜひ高橋と」
「そうだった、ごめんね、高橋くん。——ええと、そうだ」
高木が慌てた様子で荷物を漁り、何かをつかんだかと思うと、するりと手から落ちていく。持ち主があっと声を上げる間に、地面に触れて音を立てた銀色を花宮が素手で拾い上げる。高木はすまなそうに笑って受け取って、
「ええと、ごはんはもう食べたかな?」
花宮は黛を見た。黛は花宮を見なかった。銀のスプーンをしまった高木は笑顔で二人の答えを待つ。