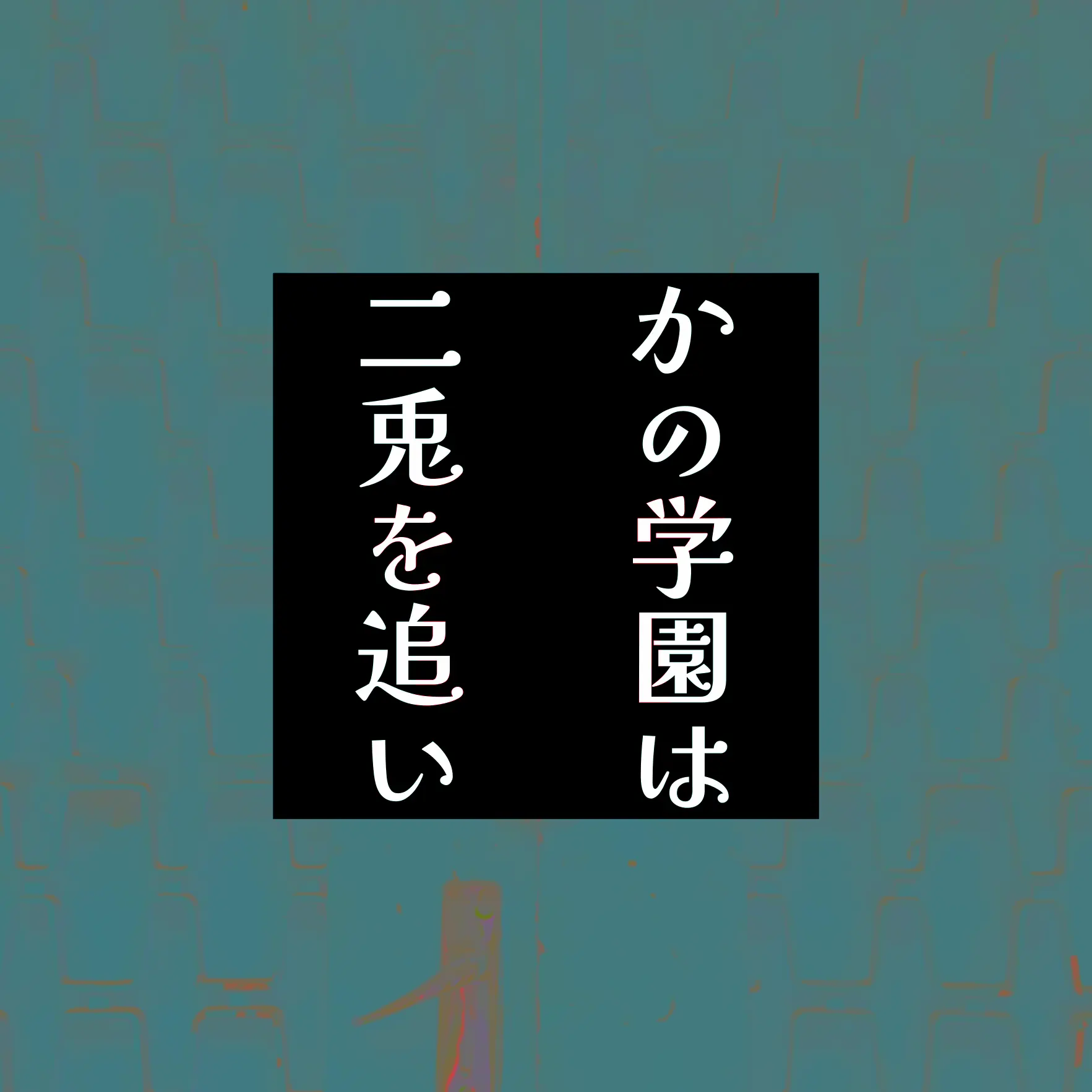かの学園は二兎を追い
一
何かというと部活動の帰りだった。無事に新入部員を迎えた新生誠凛高校バスケ部、五月、幸先はまずまず悪くない。課題がないわけでもない。そうした、ありきたりな五月の週末である。休日の練習の終わりに、三年生四名が、学校の授業の課題のために、そろいもそろって寄り道をした。
厳密にいえば、さらに、その寄り道の帰りになる。
「——キャプテン?」
主将がこのように呼びかけて、
「おまえら——」
このように答える者がいた。
はたと立ち止まって見つめ合う、四名と一名。主将に「主将」と呼ばれた彼は、名を日向順平といった。都内の大学一年生である。この大学生は、かつて誠凛高校バスケ部に在籍し、主将を務めていた。諸般の事情により、期間は一年生の時分から三年間におよぶ。現三年生四名にとって、日向は、いまだ主将の肩書の色濃い存在だった。
喜色満面の三年生一同に、日向もまた笑みを浮かべて対峙する。後輩と、卒業した主将と。
「久しぶりだな」
再会した者たちは、他愛のない話をした。
「練習試合でもやったのか」
「いえ、練習の帰りではあるんですけど、ちょっと国語の課題で美術館に」
「あー、あったな、そんなの。それで、こんなとこにまで」
まだ五月、久しぶりとはいっても、わずか二か月くらい会わなかっただけ。されど二年間ほとんど毎日のように顔を突き合わせていた相手を、とうとう見かけることもしなくなった二か月間は、想像以上に長い月日であったらしい。些細な授業の話題とあわせて日向は否が応でも高校生活を思い出し、一方で三年生は日向の服装に注目した。
同年代の男子学生の私服としては何の変哲もない、しかし日向という人物のこととなると珍しい装いに見えてならない。なにせ誠凛高校には指定の制服があって、休日の部活動で会っても皆が似たり寄ったりの運動着だ。私服を見る機会がなかったとも言わないが、主将の肩書と同様に、印象の強い姿はどれも制服を着ている。
そうして後輩は、日向という大学生を見る。見慣れぬ私服のかつての主将は、両手に買い物袋を提げていた。
「買い出し、ですか?」
尋ねつつ後輩は、先輩の進学先を思い浮かべた。ここは誠凛高校から遠く、生徒の行動圏を大きく外れており、同様に日向の実家からも距離があった。にもかかわらず、日向の買い物袋は大きく、おまけに長ねぎが差さって見えた。同時に、日向本人から知らされていた大学の名前なら、これらの違和感を簡単に解消できることにも、すぐに思い当たる。
長ねぎと、さらには生魚のパッケージも透けていたけれど。
日向は肯定した。
「そんなもんだ」
呼び止めたことを謝れば、近くだから気にするなと返ってくる。
後輩は心底からの申し訳なさを抱えながら、再び尋ねた。
「自炊、されるんですね」
「——そういえば、言ってなかったはずだよな」
日向は急に気まずくなったが、答えをごまかすつもりにはなれなかった。
「実家を出たんだ」
部活動の練習があった、ありきたりな週末の、とある夕暮れの再会である。
二
それから、なりゆきで、日向は後輩四名を自宅へ招いた。近くだからと言っていたのは本当で、歩いて十分もしないうちに到着した。学生寮ではないようだが、ありきたりに集合住宅の一室が彼の住まいらしい。何でもないように先導する日向の後ろで、後輩はどぎまぎする。ありきたりに集合住宅の一室、だけれども、まず一階でエントランスが彼らを待っていた。
思いのほか立派な住居だと、後輩のひとりは緊張した。先輩の家庭環境どうこうを邪推したわけではなく、単純に彼自身の経験から安アパートなどを想像していたのだ。今は五月といえども高校三年生。家庭でも進路の話題は出て、そこで住居の話もする。彼の家族が言ったことには、進学で私立なら実家から、公立なら寮か安アパートだと。
男子だからオートロックは不要だとか、間取りはワンルームだとか。それもこれも合格してみないと始まらないことだけれど。彼の前に現れた生身の大学生は、共用のエントランスで暗証番号を入力し、エレベータで五階へ上がり、五〇六号室の扉を開いた。角部屋の1LDKだった。
靴を脱いで、玄関マットを踏み、スリッパを履き、扉の並ぶ通路を抜ける。と、フローリングにダイニングテーブルと、キッチンと、奥にソファとローテーブルと、それからテレビ。よく片付いた室内だなと思えば、そういえば主将は外で待たせることもなく部屋に上げてくれた。ローテーブルの上には、ディスクが放り出されていたけれども。
日向は後輩たちをテレビのあたりに通して、彼自身はキッチンで買い物の始末をして、一旦、知らない扉の奥へ姿を隠した。おそらく寝室だろうと想像しつつ、後輩たちはおとなしくローテーブルの周りに腰を下ろす。ちょうど四人分のクッションがあったけれど、それぞれその横に正座した。
日向はすぐに戻ってきて、五人分のコップをテーブルに並べた。
「クッションあるぞ。ソファも二人は座れる」
そういうわけで、クッションが二つ空き、その片方に日向が座った。ディスクも回収された。
「大河の録画だよ。たまってんだ。全然見れなかったから」
「やっぱ三年って忙しいんですね」
「まあ、進学するのに冬までやるって言ったら、先生も相当言ってきた」
このように、まもなくバスケットボールの話になった。
陽泉もびっくりのセンターが入ったとか、桃井もびっくりのマネージャーが入ったとか、新しい監督がよく黒子を運用してくれるとか。陽泉高校というのはイージスの盾の異名を持つ絶対的な防御力の強豪校で、桃井さつきというのは厄介な支援能力で有名なマネージャーで、そして黒子テツヤは今まさにこの部屋にいる。
黒子は並外れて支援の得意な選手である。一方で、その支援技術は極めて特殊なありかたをしていた。いっそ特殊能力と称して何らの問題もないような。言い換えれば、並外れて扱いの困難な選手である。
諸般の事情により、日向たちの引退に伴って監督も交代になった。新しい監督と黒子の関係は、大きな懸念事項のひとつだった。しかし幸いにして新しい監督は、この特殊能力とその能力者を擁するチームに、たいへん真摯に向き合ってくれたということだ。改めて聞いて日向は我がことのように安堵し、またこの監督を紹介してくれた人物に心の中で感謝した。
「キャプテンも、またバスケ部に入ったんですか」
テレビの台の奥にバスケットボールも転がっていた。それとも、日向の進学先は、スポーツにも力を入れていることで知られている。
いずれにせよ日向は、後輩たちにうなずいて答えた。ちょうど一週間前、ゴールデンウィークのあたりには大会もあった。日向は試合に出られなかったが、新しいチームメイトとして、共通の知人がコートに立っている。後輩たちが驚いてみせたり訳知り顔でうなずいたりしたことは、日向をおもしろい気持ちにさせた。数週間前にまったく同じ反応をしたものである。
しばらく大学のバスケットボールのことを話して、また高校のバスケットボールの話もして、といったところでキッチンから電子音が聞こえてきて、日向がそちらへ引っ込んだ。後輩たちは、いよいよくるぞと、つばを飲んだ。なりゆきで先輩の家にお邪魔した。何かというと、高校時代に料理をしなかった大学生の自炊に、彼らが興味を示したことが発端だった。
興味を示したといっても、自炊をされるんですねと言ったばかりだが。言われた大学生は、少しのやりとりの後に、俺は飯をつくるぞと宣言した。いや後輩たちも魔が差して、炊きつけたり炊きつけなかったりした。結果、今、俺はやってやるぞとぶつぶつ意気込む先輩を、後輩四名が心配して覗き見たり、顔を見合わせたり。
——大丈夫だ。俺たちは恐るべき事態を体験したことがある。そしてキャプテンも。まさか合宿の二の舞は演じまいて。
まあ、諸般の事情に、よる。四名と一名は、とある悪夢を共有した、はずである。それによると、この悪夢は絶対確実に今晩の日向に影響を与えている。ええと、それはそれとして、これは特に関連するわけでもない話題だが、今年の新人マネージャーはレシピのとおりに調理を進めることができ、また別の新入部員は自分で弁当を用意しているという。終わり。
そういうわけで、後輩たちは耳を澄ませてキッチンのできごとを見守った。無礼は承知で、あの悪夢よりひどいことは起こりませんようにと祈っていた。
おそらく祈られていることに気づいていないだろう先輩、元主将、日向は、手を洗い始めた。そして冷蔵庫を開けて、たいした音も立てずに扉を閉めた。さらに物音のしない一分間。後輩たちの祈りは、プロテインの量の計算じゃありませんように、だ。何を計算したかしなかったか、日向はついに材料を取り出し、水を流す。
そのときだった。
玄関から音がした。いや鍵の開く音がした。後輩たちは、ぎょっとして音に顔を向けて、また誰からともなくキッチンを見た。家主は食材を洗い始めたところだった。再び、さっと顔を見合わせて、玄関に目を向ける。今や玄関は扉の閉まる音をさせていた。黒子は二人掛けのソファを見下ろして、ダイニングに目をくれた。テーブルを挟んで、椅子が向かい合って二脚。
もしかして。
観察をしなくたって、後輩の胸はどきどきと膨らんでやまない。もしかして。
先輩はまだ気づかない。いよいよ足音は部屋までやってくる。もしかして。
しかし黒子だけは、おや、と思って、
「おい順平」
確信と同時に、チームメイトの胸がしぼむ。もしかしても、もしかしない。ぶっきらぼうで低い声音、現れ出でたる百八十センチ。男性であった。後輩の頭は一回転。キャプテンは異性愛者だったし、と、男を見上げて、また一回転、二回転。
後輩の頭は忙しく、回って、回って、回って、回る。
百八十センチが、高校生の頭をじっと見下ろした。
「よりにもよって、こいつらかよ」
キュッと、小気味よく蛇口が閉まって、水の音がやんだ。——日向はようやく顔を上げた。おかえりの「お」の口は、現状を認識しては、まったく別の言葉をひねり出すしかなかった。
「おっまえ、な、——明日まで仕事って!」
「不倫女みたいな言い訳してんじゃねえよキメェ」
「ふっ——」
「ま、恨むんなら間男連れ込んだテメェを恨むんだな」
「——ダァホ! 監視してんなら先言え!」
「ンなことするわけねえだろ、バァカ!」
黒子の脳みそは、チームメイトに呼吸一つか二つかばかり先んじて、冷却を終える。もしかしなくても、もしかしない。小憎たらしい低音と、決して低いわけではない百八十センチ。その男の名前を、黒子はよくよく知っていた。二年前の霧崎第一高校バスケットボール部主将兼監督、花宮真である。
ところで、この人たちは何の話をしているのかと、黒子の頭は再び回転。彼の目は二人掛けのソファを映して、ダイニングテーブルを探しにいく。椅子がテーブルを挟んで、向かい合って二脚。
時刻は間もなく午後七時を迎えようとしている。
三
なりゆきで日向元主将先輩の家を訪ねたら、因縁だらけの花宮が帰ってきて、
「きちんと状況を説明してくれるんだろうな、順平くんよォ」
元主将先輩を「順平」と呼んでいた。
「ご友人の方、ですか」
高校生たちはものすんごい衝撃を受けて、ものすんごいことを尋ねていた。ものすんごい変な質問をした自覚はものすんごくあった。彼らは、日向と花宮の、ものすんごい因縁をものすんごく知っている。
高校生だった日向には、強い信頼で結ばれるチームメイトがいた。日向と同学年の、すなわち現高校三年生たちにとっては先輩の。木吉鉄平という、実に頼もしい人物である。
この木吉が一年生の夏のインターハイで負傷退場した。端的に言って、選手生命を脅かすような怪我だった。木吉はこの退場から一年以上にわたって療養、のち二年生の冬のウィンターカップのために復帰したものの、同じ怪我のために大会後は再び療養を余儀なくされた。それもアメリカで。木吉は、ついぞ復帰しないまま、日向は高校を卒業した。
それで花宮が何かというと、——実は木吉の負傷には犯人がいる、という。
ソファに二名、クッションに二名、ローテーブルを囲んで見守られて、日向はクッションにあぐらをかいた。やはり、首を横に振った。
「部屋が隣なんだよ」
キッチンから小気味のよい調理音が聞こえてきて、日向は示唆するようにそこを見る。日向の部屋のキッチンに、我が物顔で立つ花宮がいる。
「こっちは五〇六号室。あっちは五〇五号室」
はああ。高校生の深い息。そんなことがあったのかと、思うことはできても、納得することはできないけれど。いや当然ながら、この高校生たちを納得させる義務などは、日向はおろか花宮にもないのである。けれども日向は、もう少しだけ彼らの疑問に答えてくれた。
「親がな」
「ははあ」
「つながってた」
「ははあ」
高校生もキッチンを見た。よく知っていて、よく知りもしない花宮だ。知識のうえでは、この高校生たちより一学年上で、すなわち日向と木吉とは同学年で、
「大学も一緒で」
はああ。日向の深い息。
「バスケ部のマネージャーで」
はああ。
花宮が蛇口を開けた。水の音。日向が黙る。高校生も黙る。先輩の現状がますます不安になる。一方で、少し前に聞かされた、先輩の現在のチームメイトの名前を順に並べて、安心することもした。蛇口はすぐに閉じた。静かになった部屋で、日向も言った。
「心配すんな。うちは、霧崎第一みたいにはならないからさ」
これは、かつての日向の言葉だが。木吉はバスケットボールに最も誠実な人間である。と、するならば。花宮はバスケットボールに最も不誠実な人間である。
「——ところで、花宮が何作ってるかわかるか」
「——どちらかと言うなら、和食、じゃあないでしょうか」
「——なるほど、そうかもな?」
さて花宮は、後に一人前の親子丼とともに五人の前に現れて、空いたクッションのひとつに、どかりと座った。
四
思いのほか、味のする夕食になった。
ひとりで親子丼を食べ始めた花宮は、ひとりでテレビ番組を見た。日向は何も言わなかった。それならば、後輩にも言うことはない。テレビの画面の向こう側で、ニュースキャスターは他県の火災を話し続けた。大盛りの親子丼は、あたかも大前提のように温かくてうまい。
「今晩は親子丼の予定だったんですか」
「それか明日の晩にと思って、そいつに言いつけたんだが」
食卓に会話が生まれなかったわけでもない。
花宮ににらまれて日向は、へえそうだったんだと、表情で語った。表情で語った後は、眉を寄せた。
「魚は何だったんだ」
「テメェが明日の朝に焼くんだよ」
「聞いてねえぞ」
「今聞いたな」
花宮は、それで再び親子丼を口に運んだ。白米の上に、玉子とねぎが乗っている。
アルバイトの話もした。ちょうど四日前にバイト先が決まったところだった。だから、まだ働いてはいないのだと、日向は苦笑する。そして、ちらりと花宮を見た。高校生たちは、いやまさかと思った。けれども、そのまさかである。
「花宮、さんも、一緒なんですか」
花宮は素知らぬ顔でニュースを見ていた。
高校生たちは、おもに二年前を振り返って、現在の日向と花宮を見て、絶句するよりほかにない。
同じアルバイト、同じアパート、同じ食事、同じ大学、同じ部活動。そういえば高校生たちは花宮の学部を知らなかった。だが、ここまできたら逆に、違ったときこそ驚くことになるのだろう。——案の定、聞けば驚かない返答になったわけだが、今晩の高校生たちは、尋ねることなく食事を終えた。
帰路につくべき時間だった。
高校生たちは、お邪魔しましたと言って、玄関を出た。花宮には、ごちそうさまでしたと伝えた。花宮は振り向くことも見送ることもしなかった。日向は一緒に外に出て、駅まで歩くことにした。
「悪かったな」
共用エントランスの外で、真っ先に日向が言った。
後輩たちは首を横に振った。
「ごはん、おいしかったです」
「僕たちに言えることは、何もありませんから」
ただ、聞いておきたいこともある。
「先輩方はご存じなんですか」
日向は、うなずいた。
「俺から話した。木吉にもだ。——おまえらにも、会ったときにでも話すつもりだった。今日、俺の口から」
とんだ告白になってしまった。悪かったと、日向はもう一度だけ言った。それから来た道を振り返った。視界に見慣れた風景が広がった。日向は、もう適当にだって駅まで歩ける。
先輩と後輩は、バスケットボールについて当たり障りのない話をして、駅前で別れた。
「まさか、あんなことになっていたとは」
「僕も驚きました」
「うん、さすがに」
高校生たちは駅に入って、口々に言った。とんだ再会になってしまった。
遠出して、そこに卒業した先輩がいた。そのこと自体は素直に喜ばい。思わぬ再会だったが、進学先は都内である。こういうできごとは予想できた。だからこそ実家を出ていたことには驚きもしたのだけれど。まさか、さらなる驚きが彼らを襲うことなど、誰にも想像することはできなかった。
まさか、あの因縁の相手と、あれほど生活を共有することになっていたとは。昨日今日に始まった食事風景ではあるまい。明日の朝、あのキッチンで先輩が魚を焼くのだろう。結局、彼の料理の腕前はわからなかった。しかし今晩の様子を思えば、あの花宮が背後に立って嫌みに監視する光景があったとしても、違和感を抱くには値しない。
おそらくは、ひと月以上も続いていた。
同じアルバイト、同じアパート、同じ食事、同じ大学、同じ部活動。バスケットボール部の、マネージャー。
「あの人、本当に辞めてたんだな」
高校生は、別のことが気になって、声に出していた。
「あんなやつなのに、バスケやってる人間として聞くと、もったいない気がしちゃうんだな」
「あれでも木吉先輩と同格の選手でしたからね」
「なんで辞めたんだとは思わないけど、なんでマネやってんだ?」
「去年はバスケ部に入らなかったって話だったもんな」
「大学ではバスケ部に入ったのか」
「去年も入ってたけど、マネとしての入部だった、とか」
「——去年から故障してる、とか?」
五
玄関の扉を閉めて、廊下からダイニングへ。花宮は「キメェぞ」の声で日向を迎えた。
「何だ、『つながってた』って」
「俺は別にそんな意味で言ったんじゃねえよ!」
声を荒げる日向。対して、ふうん、と、冷めた様子の花宮。
「俺がどんな意味で言ったって?」
「だから親が——」
日向は顔を上げて、そこで言葉を切った。暗いばかりのテレビの画面、綺麗に片づけられたローテーブル、そして我が物顔でソファに沈む花宮が、黒のジャケットを身に着けていた。ほつれ破れた、黒の——作業服だ。
今の今まで気がつかなかった。
「火災のニュース、おまえだな」
だから気がついた。
花宮は肯定した。
「そんなもんだ」
今になって見れば、薄汚れた黒ずくめが、日向の目の前にいた。驚くことはない。花宮のことだった。後輩たちも驚かなかった。花宮のことだった。今にして思えば、日向は花宮の「仕事」をとやかく言ったのに、後輩たちが誰ひとりとしてそれに触れなかったことも、不自然以外の何ものでもない。だが、日向は驚かない。花宮が犯人だった。
「あいつらに——何もしてねえだろうな」
「『何か』してたら、あいつら飯も食わずに帰ってくれたとは思わねえか」
いや、いや。今にして思えば。日向と後輩たちの再会は本当に偶然だったのだろうか。国語の課題などのために、生活圏から離れた美術館を訪ねて、そこが偶然にも今の俺の生活圏内だったとでもいうのだろうか。偶然にもあいつらが今の俺の生活圏を訪れたときに、偶然にも俺が買い出しのために外出していたとでもいうのだろうか。
俺が偶然にも再会したあいつらを自宅に招いたことは、本当になりゆきに任せたできごとだったのだろうか。
もちろん、そうであったに決まっている。後輩たちは偶然にも日向の生活圏を訪ねることになって、日向は偶然にも後輩たちと再会して、なりゆきに任せて彼らを自宅に招いた。いや、日向は、後輩たちが日向と花宮について知ることを、望んでさえいた。
しかし花宮には、そういうことができる。
日向に望ませることができる。日向に招かせることができる。日向を外出させることができる。後輩たちを誘い出すことができる。
花宮には偶然を引き起こすことができる。
花宮が意図すれば、日向の後輩は、飯も食わずに帰っていった。
薄汚れた黒ずくめが、首だけを動かして、目を細めて、
「心配するなよ。俺はなんにもしてないからさ——記憶喪失の順平くん」
日向を見て、笑っていた。
それは。
日向の胸の奥にまで手を伸ばしたようだった。布と皮膚とをすり抜けて、肉と骨とをかき分ける。差し込まれた手は、黒のグローブを嵌めている。その骨ばって長い指が、やすやすと日向の心臓に触れて、つかむ。
昔のことだと言いたかった。今は違うのだと言いたかった。だから覚えてもいないと言いたかった。だから思い出したのだと言いたかった。
日向の言葉を、ひとつずつ喉の奥に押し戻していくようだった。
かろうじて絞り出した声は、「それは」と途切れて終わった。
「『それは』?」
花宮は構わず催促した。
それは。
日向が答えなくてはならないことだった。
「それは」
途切れて、花宮は口を開かない。それは。
俺は記憶喪失だった。だが、それは。
「あいつらには関係ないことだ」
日向は正面に花宮を据えた。グローブを嵌めた細長い指が、無造作に開かれた。そこから、すとんと落下する。ローテーブルの上に封筒が一通、表を向けて乗っていた。宛先が見えた。日向順平、様。
「『おにいちゃん』と『おねえちゃん』からだ」
花宮は表情を繕うことをやめていた。俺は風呂に入る。日向の耳元を、色のない声が無感動に通り過ぎる。そして日向も、落とされた封筒をただ拾い上げ、躊躇の残る手で慎重に裏返す。