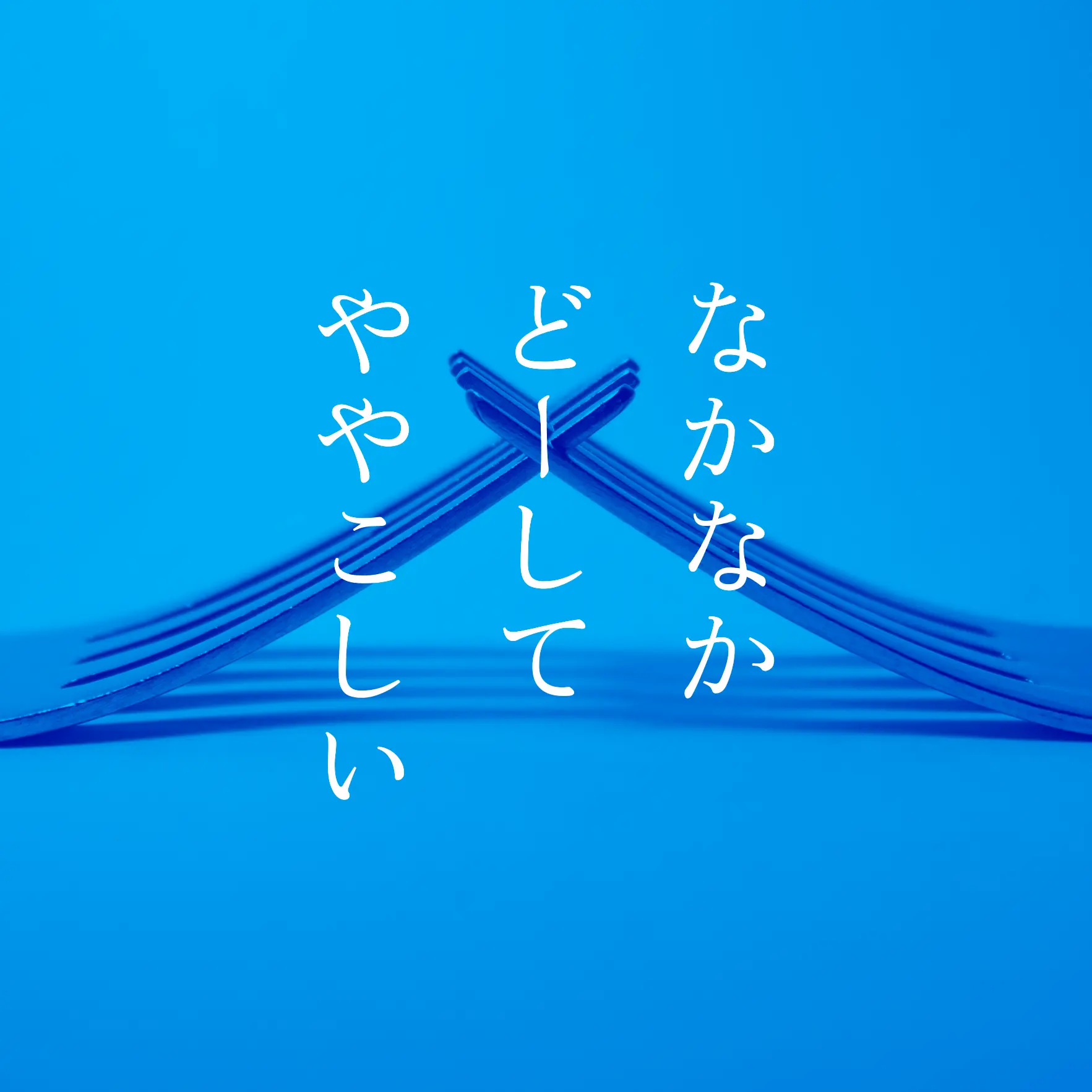バイバイ、エンジェリック・ルナティック
舌の根も乾かぬうちに。問題を避けようと選んだ言葉は「もう四か月だ」に切り捨てられた。四月十八日水曜午後九時。さよならと別れて二度と組まない黛が言った。
「温泉旅館に行かないか」
花宮真は思わず箸を止めた。従業員が通りかかる。黛が呼びかけ、
「あっ——、はい」
「同じの頼む」
「同じのですね」
従業員は花宮の料理に視線を落として確認する。立ち去る頃には花宮も海鮮丼を再び食べ始めていたが、尋ねはした。
「どなたかと勘違いされてはいませんか」
当然の疑問である。
「ライトノベル作家の鯛焼堂杏子先生が泊まるらしい」
黛の回答である。ちっとも答えになってはいない。だから何だと。花宮がそう続けることもまた当然のようだったが、彼はそれをせず、ただ黛の横に目をくれた。視界の端で黛が深々と頭を下げる。
「頼む、一緒に助けてくれ」
一分前のできごとだ。花宮の食事の向こう側に黛が突然現れた。約束もなく、そして断りもなく花宮の正面に腰を下ろす。どすんと物音をさせて、荷物も軽々と置いてくれた。黛の脇の重たげな袋である。そのとき本かと中身を推測した花宮だが、より具体的にはライトノベルになるのだろう。作家はおそらく鯛焼堂杏子。それが、だから何だという話だけれども。俺はライトノベル愛好家なんかじゃあないんです。
もちろん黛は百も承知だ。花宮はライトノベル愛好家ではない。なら何かって、
「打ち切りの危機でも?」
「命の危機だ」
ハンターである。
花宮が海鮮丼を一口食べた。黛はとがめない。ちょうど頼んだビールが届く。ごゆっくり。従業員が花宮を見る。立ち去るとすぐ、それを持ち上げた黛が、ごくり、ごくごく、ごっくん、ごとり。ジョッキを手放し、息をついた。花宮は海鮮丼をさらに一口、二口、三口。
殺されたんだ。
いくらの味が広がる口で、黛の言葉を聞き流す。
「悪霊か妖術師か吸血鬼か何かそういうのに殺されたんだ、今川大葉先生が」
もちろん花宮は今川大葉も知らなかったが、ライトノベル作家かイラストレーターの名前だろうと当たりをつける。ライトノベルの表紙が慣習的にイラストで飾られることは花宮も知っていた。口を挟まないでおくと案の定、今川大葉はライトノベル作家だった。花宮はいくらをつついた。黛も相槌など待たなかった。
「ラノベ作家の今川大葉先生が十三日に亡くなったと、SNSに投稿があった」
十六日のことだ。葬儀は身内だけで済ませたとか、急なことだったとかの、よくあるやつで、アカウントの主は同じレーベルのライトノベル作家。今川大葉の友人としても知られており、まもなく出版社からも文書が出たことによって、急速に現実を帯びていく。トレンドにもなった。
「人気作家だったしな。現在進行形の代表作『堕天使に誘惑されている!』はコミカライズ、アニメ化ときて、劇場版も制作決定——」
「したんですか」
「——アニメ一期最終話の最後に二期が発表されたら何巻まで放送されるだろうってのがあって、それ以降どんどん描写が過激になるから二期最終話では劇場版制作決定が発表されるだろうと」
「希望的観測でしたね」
「言ってろ。ファンの宿命だ」
黛がにらんでも、花宮はとんとわからない顔だ。興味がなかった。黛は憤慨を胸にしまう。これだからラノオタじゃないやつは!
花宮がライトノベルオタクだったなら、まずは一期の成功を祈って乾杯したり、『けのとと』の制作会社だから信用できると話し合ったり、したのだろうか。あいにくラノベオタクは黛だけだ。乾杯のかわりに黛は独りでジョッキをあおった。
いくら丼も届いた。従業員は花宮に一瞬怪訝な顔を向けたが、「こっちです」の声で慌てて料理を置く。
黛は箸をつかんだ。
「とにかくだ。今川大葉先生が亡くなった。友人にしろ出版社にしろ、どっちも確かな出所だ。さすがにガセじゃないってなって、——これ、うまいな。——そのうち、どいつかが十三日の小さいニュースを引っ張り出した。マンションの屋上で住人が死んだんだと」
飯をすくうと「これが本場の味ってやつか」などと表情ひとつ変えずに言った黛の向かいで、花宮は箸を置いた。かわりに端末を手に取る。件のニュースは多少調べたらすぐに出てきた。今川大葉の名前と一緒に。
花宮がニュースを見つけたことを知っても、黛は続けた。
「正確には死体が出たらしい。ってことで、ちょっとした騒ぎになって、警察が出てきた。が、他殺じゃなかった。昇降口から——屋上の昇降口の屋根にでも立って——飛び降りて、つーか転げ落ちて、打ちどころが悪く、ってのが公式見解。
それが『堕天使!』の今川大葉先生だと、どっかの誰かが言い出した。先生は珍しくもなく顔も本名も出しちゃいなかったが、それでも特定したいやつはいる。そいつらの話では、そこに先生が住んでいて、つまり今川大葉先生が自殺したんだと、そういうことになっていた。今川大葉先生は十三日に自宅マンションで屋上に落ちて亡くなった。——俺も調べた」
黛は、またいくら丼を口へ運んだ。眉も動かさずうまいと告げると、箸を再び丼へ向ける。白米の上で新鮮ないくらが輝いている。函館くんだりまで足を運んだ甲斐があったと胸中でつぶやく。
一方の花宮はジョッキをつかむと酒をあおった。音を立てて置いた。
「それで?」
続きがあることは知っていた。そうでもなければ、あきれるところだ。実際、黛は話を続けた。
「そりゃそうだ。これは一大事で、言ったろ、俺も調べてきた」
先生の。黛は最初にそう指示して、今川大葉先生のと言い直す。
「今川大葉先生の飛び降りは最初じゃなかった」
二回目という意味ではない。
「二件目だった」
ライトノベル作家の飛び降りは、先月の末にも起きている。
マンションですかと花宮が尋ねた。黛は首を横に振った。
「重要なのはそこじゃない。衛門虎先生の『バイバイ、エンジェリック・ルナティック』を知ってるか? 学校の屋上の扉を開けてみたら、よく知らない女子生徒が飛び降りようとしていたって話だ。衛門虎先生はそれが自殺の原因じゃないかってうわさされるほど酷評されたこともあるんだが、『バ、エ・ル』は満場一致の代表作でな」
黛は箸を置き、手を拭き、脇の荷物を開いて閉じた。次に現れた彼の手は、一冊の本を花宮に突き出してくる。衛門虎の『バイバイ、エンジェリック・ルナティック』だ。花宮は一度だけ黛の顔を見て、仕方なしに受け取った。黛の腕が引っ込んだ。話が再開しないので、仕方なしに冒頭も読んだ。確かに序盤で主人公がクラスメイトの飛び降りを止める事件が起きた。めんどくせー。そこまで読んだ花宮は胸中でつぶやくと本を閉じ、こちらは声に出して言った。
「今川大葉は登場人物を屋上に突き落としたことがあるかと、俺は尋ねるべきですか」
「『堕天使に誘惑されている!』は屋上に降ってくる少女を主人公が受け止めて始まるラノベだ」
「それ主人公が死にませんか」
「少女は堕天使で羽が生えてた」
「——鯛焼堂杏子は?」
「『時計仕掛けの林檎と蜂蜜と妹。』には、ヒロインが屋上で主人公に体内の心臓部を見せようとする場面がある」
グロテスクですねと花宮は言わなかった。尋ねるだけ無駄だと知っていた。実際、尋ねていたなら、黛は即座に「林檎たんは機械人形だ」と答えただろう。
クラスにやってきた転校生は、人間ではなく「宇宙から来た進化する機械人形」だった! 彼女の目的は、特別な心臓で地球の浄化を促すこと。その手伝いをしてほしいと頼まれる主人公だったが、彼はすでに別の厄介ごとを抱えていて——。宇宙から来た機械人形、体に取り憑いた幽霊、屋上に降って湧いた妹! 不思議で甘くて波乱万丈な学園生活を描いた『時計仕掛けの林檎と蜂蜜と妹。』劇場版第三弾制作決定!
おめでとう。ありがとう。ありがとう。ありがとう。エンドレス。黛はこの『けのとと』と鯛焼堂杏子先生に一生ついていく所存である。
「へえ。人気があるんですね」
花宮は『けのとと』で検索した。正式名称はクソ長かった。しかし一発で出てきた。題名のひらがな部分を抽出してつくった略称だろうが、ファンでも長く感じるらしい、などと考えつつ、メディアミックス情報を読んでいく。劇場版制作が一種の成功であることは、ライトノベルに明るくない花宮にもわかる。黛の懸念も察することはできた。
ヒロインを屋上に落とした今川大葉が、屋上に落ちて死亡。ヒロインを屋上から落とそうとした衛門虎は、屋上から落ちて死亡。それなら『時計仕掛けの林檎と蜂蜜と妹。』は——。正体を明かされた主人公は、一度はその告白を疑ってみせた。すると転校生は「なら心臓を見せてあげる」といかにも機械的な情緒で制服を脱ぎだすのだ。このイベントは他ならぬ主人公によって中断されたけれど。
「では」
花宮が端末から顔を上げた。
「三件目の自殺に関して伺いましょうか」
「そうだ、それが今日のニュースだったな」
小説家の東形京人さん死去。三十四歳。『屋上病院——医神と雇われバトルナース——』
「短編連作第一話はバトルナースヒロインへの屋上オペですか」
「自宅マンション屋上で心筋梗塞を起こして亡くなったそうだ」